第70回テーマ
大阪市立大学「いのちを守る都市づくり」その2「災害時のいのちを守る術」
平成27年3月1日に設立された「都市防災教育研究センター(CERD)」では、東日本大震災の教訓を活かして災害死ゼロを目指し、地域住民が自ら災害リスクを学習するためのツール開発、防災まち歩きや災害対応訓練プログラムの開発、防災環境改善の実践、災害時の医療、避難生活における健康管理、避難に必要な体力の増進プログラムの開発などに取り組んでいます。今回はCERD 災害対応ユニットの取り組みを紹介します。

渡辺 一志(都市健康・スポーツ研究センター 教授)
【キーワード】 ■自助・共助 ■コミュニティ ■災害対応力
| 講演者/タイトル | ||
|---|---|---|
| 講演内容 | ||
| ◆横山 美江(看護学研究科 教授)/「セルフケア能力向上のためのコミュニティ防災教育プログラムとその効果」 | ||
 CERD のヘルスケア部門では、セルフケア理論を災害看護に応用。市民が災害から自身で身を守る力を身につけ、自助・共助における行動力を高め、災害時にもサバイバルできるような防災教育プログラムを作成し、地域住民を対象に実施している防災教育のプログラム内容と学習効果について紹介。 |
■セルフケア ■感染症予防 ■便秘・下痢予防 ■持病管理 ■赤ちゃんの健康 |
|
| ◆今井 大喜(都市健康・スポーツ研究センター 講師)/「災害時の避難に必要な体力について考える」 | ||
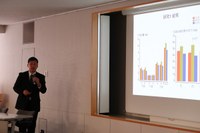 政府地震調査研究推進本部は南海トラフを震源域とする大地震の発生確率を「30 年以内に70%程度」と推定。大規模な津波被害が予想され、津波来襲までの避難行動が重要となるため「避難」に注目した体力評価をもとにした一次避難に必要な体力について検討。 |
■自助・共助 ■避難体力 ■水平避難 ■垂直避難 ■下肢筋力 |
|
| ◆野村 恭代(生活科学研究科 准教授)/「福祉的配慮のある避難所づくり」 | ||
 日頃からのつながりを基盤とした、人と人との「支え合い」が災害発生時に力を発揮します。地域のなかに存在している、何らかの配慮が必要な方、生活支援が必要な方への避難所での「福祉的配慮」とは何か、日常生活における福祉的な配慮について紹介。 |
■福祉的配慮 ■生活のしづらさ ■つながり |
|
| ◆由田 克士(生活科学研究科 教授)/「ローリングストックによる水・食料の備蓄」 | ||
 効率の良い備蓄方法は?ローリングストック法は普段使用している保存性の高い食品(乾物、缶詰、レトルト食品など)を一定量ストックしつつ、賞味期限までに順次消費し、買い足していくという無駄なく一定量を継続的に備蓄可能な方法です。今後起こりうる大災害に備え、比較的容易にできる備蓄方法について紹介。 |
■食糧備蓄 ■ローリングストック ■栄養 ■食生活 |
|
次回、平成29年7月10日(月)開催の第71回「オープン・ラボラトリー」『大阪市立大学「いのちを守る都市づくり』その3「大阪の防災・減災に向けた取り組み」についてはコチラをご覧ください。




